2 アジア通貨危機支援の全体像
2.2 実績日本は、アジア通貨・経済危機への対応として、これまでに総額約820億ドルのアジア支援策を表明した。その内訳を見ると、
- 1997年7月から98年11月末までに表明したアジア支援策:440億ドル、
- 新宮沢構想に基づく資金援助:330億ドル(短期資金需要への対応:150億ドル、中長期資金支援:150億ドル、アジア開発銀行アジア通貨危機支援基金への拠出:30億ドル)
- 特別円借款:50億ドル
図 2-1 日本によるアジア通貨危機支援の実績(1999年12月現在)
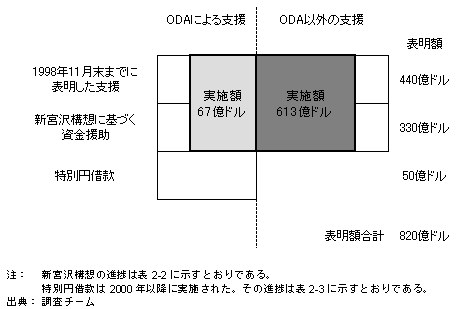
ODAとして実施された主な案件は、大きく、1. 経済構造改革支援、2. 社会的弱者支援、3. 人材育成支援の3分野に分類されるが、それぞれについて実績を概観する。
2.2.1 経済構造改革支援
これは、各国が直面する課題である金融セクター改革、市場経済の効率化のための制度改革など、経済構造改革を推進するための支援である。具体的には、経済危機の影響を受けたアジア諸国が、世界銀行、IMF、アジア開発銀行等の国際金融機関との合意の下、これら機関と協力して行う構造調整政策に取り組んでいけるよう、円借款を通じた支援を行っている。これには、日本が独自に被援助国政府との政策協議等を通じ合意した経済改革政策の実施を支援するための円借款供与も含まれている。
これに加え、ノン・プロジェクト無償資金協力の実施およびアジア諸国が経済構造調整政策を推進できるよう、構造改革に関する政策アドバイザーとして政府関係者を各国に派遣した。同時に、経済基盤強化のためのインフラ整備や、農業・農村整備等ハード面の整備に加え、裾野産業育成や適切な経済・社会運営のための人材育成、より高度な技術移転等ソフト面の支援を通じた経済構造改革のための支援を促進した。主な実施案件としては以下が挙げられる。なお、援助額は1999年8月現在の値である。
円借款による経済構造改革支援:3,368億円(約27.1億ドル)
保健・栄養セクター開発計画(インドネシア)、経済復興・社会セクター・プログラム・ローン(タイ)、メトロマニラ大気改善セクター開発計画(フィリピン)、経済改革支援借款 (ヴィエトナム)など
ノン・プロジェクト無償による支援:145億円(約1.2億ドル)
実施国:フィリピン、ラオス、タイ、インドネシア、ヴィエトナム
円借款によるインフラ整備および農業農村支援:約2,420億円(約19.8億ドル)
地方開発・雇用創出・農業信用計画、農業セクターローン(タイ)、ポートディクソン火力発電所リハビリ計画(マレイシア)、地方上水道整備計画、農地改革インフラ整備計画(フィリピン)、他12件
円借款によるその他支援:約98億円(約8.1億ドル)
工業部門強化計画、交通企画管理計画(タイ)、中小企業育成基金計画(マレイシア)、工業・支援産業拡充計画2 、産業公害防止支援政策金融計画2、ピナツボ火山災害緊急復旧計画、パッシグ・マリキナ川河川改修計画(フィリピン)等
円借款案件等の円滑な実施を確保するためのローカルコスト支援:約364億円(約2.8億ドル)
既往案件内貨融資(タイ)
金融部門の強化および中小企業振興のための支援
貿易金融強化(貿易金融円滑化および輸出銀行設立)のための専門家派遣・研修員受入、中小企業振興のための専門家の派遣(インドネシア)、中小企業振興のための専門家の派遣、家内工業振興のための研修(タイ)
2.2.2 社会的弱者支援
アジア経済危機では、多くの国において、輸入に依存する食糧や医薬品・医薬品原料などの価格高騰、緊縮財政下での教育費・医療費や公共料金の値上げ、各種補助金の削減などの結果、その負担がとりわけ貧困層、高齢者層、増大する失業者など社会的弱者に大きくのしかかった。日本は経済危機下のアジアへの支援を進めるにあたり、「社会的弱者支援」の視点が重要であるとの強い認識を表明しており、経済危機下での支援に当たって、栄養摂取や保健医療など人々の基礎的生活状況に十分配慮すべきこと、社会的弱者にもたらす影響の把握に努め的確に対応すべきことを重点政策とした。この観点から、従来行ってきた貧困対策に加え、特に、雇用対策、保健・医療サービスの拡充等基礎的生活分野(BHN)への支援、農業部門の強化、更には、社会的安全網(ソーシャル・セーフティ・ネット)の構築等のために、円借款のセクター・プログラム・ローンの見返り資金4や、ノン・プロジェクト無償およびその見返り資金を活用するなどによって、総額約1330億円の支援を実施した。主要な支援は以下のとおりである。
- インドネシアに対する医薬品等購入のための緊急無償援助:約40億円
- インドネシアに対するコメ支援政府米70万トンの貸付および貸付米の輸送費等支援:約73億円および無償援助5万トン程度:供与限度額23億円
- インドネシアに対する食糧増産援助:15億円
- 保健・栄養セクター開発計画(インドネシア、円借款):353億円
- ソーシャル・セーフティ・ネット借款(インドネシア、円借款):452億円
- 経済復興・社会セクター・プログラム・ローン(タイ、円借款):300億円
- 貧困地域中等教育拡充計画(フィリピン):72億円
2.2.3 人材育成支援・留学生支援
中長期的な経済発展のためには、人材育成や経済運営、制度改革などの能力強化に向けられる支援は重要である。日本は、東南アジア各国に対する人材育成等のための協力を重視してきているが、金融危機に直面して改めて経済の持続的発展に資する分野に焦点をあて、97年12月に、5年間で2万人の人材育成支援を目標とする「日ASEAN総合人材育成プログラム」を表明し、その中で、1. 将来の政治的・社会的リーダー、2. 経済・社会運営に関わる行政官・地方行政官、3. 民間実務者・技術者を中心とする人材育成に重点的に取り組んだ。1999年5月時点で、この目標は既に達成されており、質の高い人材育成を進めるべく引き続き協力を行っている。更に、JICAを通じた緊急人材育成支援のほか、産業の中核を担う人材に対する1万人規模の現地研修の実施等、この分野での協力を強化している。
また、留学生への支援として、97年12月、人材育成を支援するための円借款(留学生借款)について一般の条件よりも特別に優遇された貸付条件を導入し、日本への留学生派遣など人材育成に役立てることとしたほか、緊急無償資金協力を実施し、日本への留学事業の継続が可能となるよう支援を行っている。また、99年度より、二国間関係強化の観点を踏まえ、途上国による日本への留学生派遣事業を支援する留学生支援無償が導入されている。今後とも、経済政策策定支援や金融・経済に係る法整備支援・制度造り支援のための政策アドバイザー派遣、専門家派遣や研修員受け入れなどを通じた人造り協力を引き続き積極的に行うこととしている。その際、日本の企業関係者の経験とノウハウを最大限に活用していくこととしている。
これら人材育成および留学生支援に関して、総額520億円(約4.3億ドル)の支援が実施されている。主な実施プログラムは以下のとおりである。
人材育成支援
- 日・ASEAN 総合人材育成プログラム(5年間で2万人)
- JICA ベースで追加的に1,000人の緊急人材育成:26億円(約2,000万ドル)
- 海外技術者研修協会が追加的に1,000名以上の研修生受け入れ:20.7億円(約1,800万ドル)
- 産業の中核を担う人材に対する1万人規模の現地研修:28.2億円(約2,400万ドル)
- 円借款を活用した人材育成事業:タイ:産業人材育成センター建設事業:25.73億円(約0.2億ドル)、および、マレイシア:サラワク大学建設計画:185.49億円(約1.54億ドル)
留学生支援
- 政府派遣留学事業継続のための緊急無償援助:マレイシア 約4.5億円(424万ドル)、タイ 約1億円(95万ドル)
- 円借款を活用した留学生支援:マレイシア東方政策 140.26億円(1.16億ドル)、高等教育借款基金計画2 52.85億円(約0.44億ドル)
- 東南アジア諸国および韓国からの私費留学生を対象に一時金5 万円の支給:3 億円(約230万ドル)
- 東南アジア諸国および韓国からの私費留学生向け奨学金の支給および留学生宿舎建設奨励金の交付:32億円(約2,500万ドル)
4 「見返り資金」とは、日本政府が円借款を貸し付ける際、途上国政府(この場合はインドネシア政府)が準備する同額のルピアのことである。このルピアはインドネシア政府が事業を実施する資金に用いられる

